【出張レポ-ト 2024春♯2】ドメーヌ・フルーロ=ラローズの歴史と魅力編
今回の【出張レポ-ト 2024春♯2】ドメーヌ・フルーロ=ラローズの歴史と魅力編では、豊かな収穫と壮大なカーヴ、特別なモノポールと日本市場との関係、歴史的な評価を受ける畑と多様な栽培についてをお届けいたします!
ロマネ=コンティも眠った邸宅──ドメーヌ・フルーロ=ラローズの系譜と物語
ドメーヌ・フルーロ=ラローズは、1872年に設立した歴史あるドメーヌで、現在は4代目の二コラ・フルーロ氏がワイン造りを行っています。配偶者の久美子夫人は日本人で、そうした縁からこのドメーヌを知る人も少なくありません。あるいは、当時はまだ皇太子だった現天皇が日仏友好160周年の記念して、フランス政府による招待で公式訪問された折に視察をされた、というニュースで知る人もあるやもしれません

(外壁に残る「Domaine René Fleurot」の刻印。現在のドメーヌ・フルーロ=ラローズの前身にあたる)
そんなフルーロ=ラローズは、特級のモンラシェやバタール=モンラシェを代々所有する名家でもあり、そんな名家を物語るエピソードとして、現在のお屋敷を取得することになった経緯があります。実はこの現在の住居兼ドメーヌとなっているお屋敷、もともとは130haほどのブドウ畑を所有した大地主で、1911年までロマネ=コンティを醸造したジャック=マリー・デュヴォーが1843年に建てたお屋敷だったのです。この建物は、3階建の醸造所兼住居で、高さは22mほどという当時としては豪華な造りが特徴です。地下も2階分しっかりと掘られており、延べ床面積は1400平米にもなります。
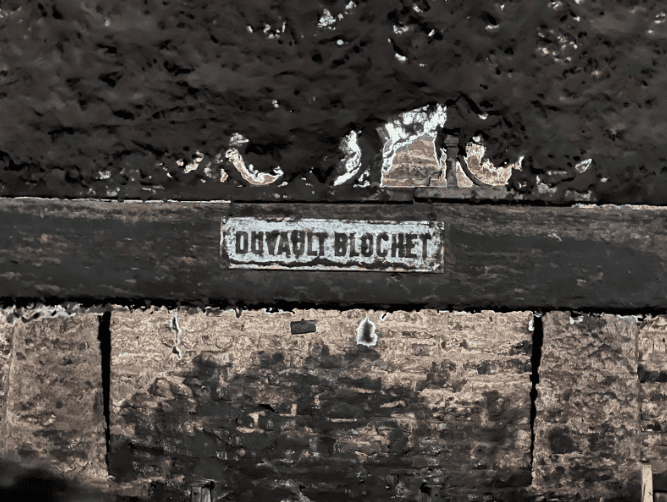
(DRCのヴォーヌ=ロマネ一級のキュヴェ名でもあるデュヴォー=ブロシェの名が刻まれる)
当時は、ロマネ=コンティの畑で収穫されたブドウをポマールの駅舎で馬を変えて、サントネまで運び込み、この屋敷で醸造から瓶詰までが行われ、まさしくロマネ=コンティが造られ、このカーヴで寝かされいたのです。
その後ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ=コンティが設立されるにあたり、お屋敷はフルーロ家に金貨で売却されるはこびとなりました。
ナチス占拠をも耐えた、最大2,000樽保管可能な圧巻の熟成庫
現在ブルゴーニュの地下カーヴは機械換気を採用することが多い中、機械を使わず換気が可能なのがこの地下2階分にもにわたる立派なカーヴの最大の特徴です。
カーヴの中は通年11.5℃ほどをキープしており、夏の暑い時期も冬の寒い時期も一定の温度に保つことができるのは、とりわけ大きなこの地下空間のおかげです。地上からの距離もしっかりとあるため、外気の影響も受けにくいためです。
カーヴは樽を積み上げて保管すれば最大で2000樽ほど保管可能で、1000樽を2ミレジム分キープできるのだとのことです。
1000樽で約30万本ほどとなりますので、ブルゴーニュの一般的な生産者の平均年間生産量が年間4万本程度であることを、また、中堅ネゴシアンのシャンソン・ペール・エ・フィスの平均年間生産量が20万本程度であることを鑑みれば、いかにこのカーヴが一般的な生産者のレヴェルにおいてはオーバースペックかというのが感じ取れます。

(熟成庫の様子。特に上部にこれだけ広々としたカーヴは珍しい)
もちろん、ロマネ=コンティをはじめとした大地主だったジャック=マリー・デュヴォーの時代には、まさしくこうした広さの必要に迫られたわけです。第二次世界大戦下においては、これだけ立派な建物だったこともあり、ナチス・ドイツに占拠されてしまった不運な歴史がありますが、不幸中の幸いだったことは、貴族出身でもあったこの建物を占拠した部隊の指揮官による厳命により、セラーの中の稀少なワインについては、決して手を付けてはならない、とのことで、当時のモンラシェ等の特級ワインについては、略奪の難を免れたのだといい、なんとそのころのワインのなかには、今なおドメーヌに現存しているものもあるのだとか。
ちなみに、この自慢のグラン・クリュ、モンラシェとバタール=モンラシェについては、2020年からマグナムのみの瓶詰となりましたが、かつては、アピシウスに初めて特別製のグランクリュのハーフボトルを納品したこともあり、今では良い思い出になっているとのことでした。
やはり偉大なワインというものは、適切な熟成を経て適正な状態で飲んでもらいたいという思いから、熟成スピードが遅く、最適な熟成スピードと言われるマグナムボトルのみでリリースすることにより、ベストな状態で味わってもらいたいという強い願いが込められています。そんな時の流れを忘れてしまうような熟成庫でした。
(熟成庫に並ぶ瓶詰された古酒。積みあがったほこりが時の流れを物語っている)
2021年の不作を経て──7haの畑が迎えた実りの年
ドメーヌが所有する畑は全部で7haで、平均的な規模にあたります。
裏手にはクロ・ド・パス・タンという2.5haのモノポールがあり、ドメーヌの顔ともいうべき存在です。
2023年はひさびさの豊作の年となったとのことで、近年は天候不順が断続的に起こっていたこともあり、ほっと胸をなでおろすことができたとのことでした。直近だと、2021年のシャサーニュは生産量が75%減となってしまった経緯もあり、生産者にとってはよほどの安堵となりました。
そうした観点から、2021年のシャサーニュ、ピュリニィ、ムルソーの白の不作を原因とする供給不足については、若干の改善がみられそうです。

(ドメーヌの顔ともいうべき存在、2.5haのモノポールのクロ・ド・パス・タン)
過小評価されがちなシャサーニュ赤――かつてはグラン・エシェゾーと同じ価格で取引された記録も
ドメーヌに残されている古い勘定帳をひらけば、ドメーヌのモノポールでもあるアベイ・ド・モルジョの区画については、1940年台まではモンラシェやグラン・エシェゾーと同じくらいの価格で取引されていた記録が実際に残っており、モルジョ集落全体として、粘土質の畑で赤にも向くという評価を受けていたようです。過去の勘定帳から当時の表象を分析する、というのは、リュシアン・フェーヴルやフェルナン・ブローデルといったアナール学派歴史学が行った一連の心性史研究が思い出されますが、そうした意味でも、このアベイ・ド・モルジョの区画というのは、かつては比類を見ないほど優れた畑として高く評価されていたことがうかがえます。
ところで、AOCシャサーニュにおける赤ワイン用ブドウの栽培面積は2004-2008年の平均で約38%を占めたのが、2017-2021年の平均では約28%と、13年の間に10%ほど下がりました。もう少し古いデータではたしかシャサーニュの約半量は赤といわれていましたので、世界的な需要に合わせてシャルドネへの植え替えが急速に進んでいます。しかしながら、ジャン=クロード・ラモネやミシェル・ニエロンの村名格シャサーニュの見事な赤を口にしたことがある人ならだれでも、シャサーニュの赤ワインのポテンシャルの高さに疑いを持つ人はいないでしょう。
こうした事実や歴史的経緯に加え、比較的粘土質の土壌が多いモルジョ集落周辺の地理的条件を考えれば、実際は赤ワインを生産したほうがより高品質なワインができる可能性は十分にあると考えられます。そうした意味でも、このアベイ・ド・モルジョをはじめとしたモルジョ集落の畑というのは、再評価されてもよいでしょう。
現在においては白の方が高値で売れるそうですが、ドメーヌ・フルーロ=ラローズでも植え替え時に引き続き赤を植えることとなりました。理由はご主人の「だって赤が植わってたんだもん」、という一言で決まったのだとか。
現状の栽培比率は、赤白半々で、かつてはクリマ全域をモノポールとしていた時代もあったのだとか。
ドメーヌ・フルーロ=ラローズが現在持つモノポールは2つあり、ひとつはアベイ・ド・モルジョからもほどちかいシャサーニュ一級のクロ・ド・ラ・ロックモール。こちらは、地中に石灰岩の岩盤があるとのことで、白ワインに適したテロワールを持っているようです。
また、ドメーヌの裏手にあるクロ・デ・パス・タンの畑も同様に単独所有をしています。こちらの畑には白ブドウが1/4、黒ブドウが3/4ほど植えられているとのことでした。
以上、現地ならではのドメーヌの歴史や、直近の生産状況にのみならず、名家ならではのかつての勘定帳から伺える歴史的評価の変遷、畑の土壌の話まで、興味深い訪問となりました。
>>>次回は【出張レポ-ト 2024春♯3】 ドメーヌ・アラン・ビュルゲ 2023年新樽試飲編 をお届けいたします。どうぞお楽しみに!
(出張レポート:川﨑大志 編集:WineBank )


